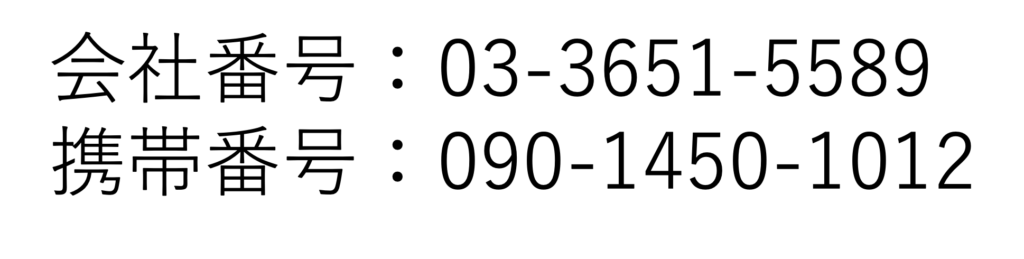廃棄物とは売却や利用価値のないもののことで、不用物や汚物などを指しています。
家庭から出される廃棄物は一般廃棄物と呼ばれ、事業活動によって生じた廃棄物は、内容によって一般廃棄物か産業廃棄物かに分けられます。
産業廃棄物は一般廃棄物と違い、特定の許可を得ている産業廃棄物処理事業者に処理・処分を委託しなくてはいけません。
今回は、区分が難しいと言われる一般廃棄物と産業廃棄物の違いと、産業廃棄物の処理・処分方法や産業廃棄物処理に欠かせないマニフェスト制度についてまとめました。
産業廃棄物の処理・処分を行いたいと考えているのなら、ぜひ参考にしてください。
産業廃棄物とは
産業廃棄物は略して「産廃」(さんぱい)と呼ばれることもあり、事業活動で生じた廃棄物のうち、法令で定められた20種類を指しています。
つまり、事業活動の中で発生する廃棄物は一般廃棄物と産業廃棄物の2種類に分けられるということです。
ここで言う事業活動には、製造業や建設業だけでなく、商業活動・オフィス・学校などの公共事業も含まれます。
代表的な産業廃棄物には、「燃え殻」「金属くず」「ゴムくず」などがあり、これらは少量であっても一般廃棄物と一緒に処理・処分できません。
また、以下のものは廃棄物処理法の規制対象外となります。
- 気体状のもの
- 港湾、河川などのしゅんせつに伴って生じる土砂その他これに類するもの
- 放射性物質及びこれによって汚染されたもの
- 土砂及び専ら土地造成の目的になる土砂に準ずるもの
- 漁業活動に伴って魚網にかかった水産動植物などであって、当該漁業活動を行った現場付近において排出したもの
- 有価物
廃棄物の中でも、爆発性・毒性・感染性などがある産業廃棄物は「特別管理産業廃棄物」・一般廃棄物は「特別管理一般廃棄物」に区分され、「特管物」と略されることもあります。
特別管理産業廃棄物や特別管理一般廃棄物は、排出の段階から最終処理までの間の扱いに常に注意が必要で、通常の産業廃棄物とは別の処理基準が定められているのです。
さらに、特別管理産業廃棄物の排出事業者は、特別管理産業廃棄物管理責任者を設置しなくてはいけません。
特別管理産業廃棄物の代表的なものには「廃油」「廃酸」「廃アルカリ」などがあります。
一般廃棄物と産業廃棄物の違い
一般廃棄物と産業廃棄物は、その廃棄物の排出元・廃棄物自体の内容だけでなく、廃棄物を処理するための責任の所在も変わります。
一般廃棄物は市町村に処理責任があるのに対し、産業廃棄物は排出事業者に処理責任があるのです。
この責任の所在を一般的に「排出者責任」または「排出事業者責任」と呼びます。
そのため、排出事業者は産業廃棄物の処理・処分を市町村に依頼できません。
排出事業者が産業廃棄物を処理・処分するには、都道府県の「産業廃棄物収集運搬業」「産業廃棄物処理業」の許可を受けた産業廃棄物処理事業者に委託する必要があるのです。
また、産業廃棄物には量的な規定が設けられていないことから、個人事業主のような小規模な事業者や、生じた産業廃棄物がごく少量であっても同様の扱いをしなくてはいけません。
多くの事業主にとって産業廃棄物の処理・処分は、大きな課題であると言えるでしょう。
産業廃棄物の種類
産業廃棄物は事業活動で生じた廃棄物のうち、法令に該当する20種類であるとお伝えしました。その20種類は下記の表の通りです。
区分は「あらゆる業種から排出されるもの」と「業種が特定されるもの」に分かれるため、自社の業種によって産業廃棄物と一般廃棄物の境目も違ってくると言えるでしょう。
産業廃棄物の処理方法について
先ほどもお伝えしたように、産業廃棄物は市町村に処理・処分を依頼することができず、「産業廃棄物収集運搬業」「産業廃棄物処理業」という許可を都道府県から受けた産業廃棄物処理業者に処理・処分を委託する必要があります。
産業廃棄物処理業者での一般的な産業廃棄物の処理・処分の流れは、大きく分けて3つのステップに分かれます。
収集・運搬
産業廃棄物を適切に処理する場所に移動するために、産業廃棄物処分業者が産業廃棄物を収集・運搬します。
産業廃棄物の収集・運搬には都道府県からの専用の許可が必要であり、荷積みと荷卸しの都道府県が変わる場合は、それぞれの都道府県から許可を得ることになります。
また、この許可の申請や管理は産業廃棄物処理業者が行うものです。
中間処理
中間処理では、収集・運搬した産業廃棄物を適切に最終処分するために、分別します。減量化を目的とした粉砕や脱水を行うこともあるでしょう。
その他にも焼却・中和など、このステップで実施される処理を総称して中間処理と呼びます。
産業廃棄物を少なくする・再利用可能な資源を取り出すなどの作業を含む重要な工程です。
中間処理では一時的に産業廃棄物を保管し、同じ処分方法の産業廃棄物をまとめて最終処分する場合もあります。
次の項目でも説明しますが、現在は最終処分場の不足が大きな問題になっており、中間処理で産業廃棄物を減らすために多くの取り組みが行われています。
最終処分
最終的に産業廃棄物を処理・処分するステップです。その方法は産業廃棄物の種類や産業廃棄物処理業者によって変わりますが、地中に埋め立てる・海に埋め立てるなどの方法があります。
最終処分を行う土地には限りがあるため、産業廃棄物自体を少しでも中間処理段階で減らすことが大切です。
海面埋め立ては地方公共団体が主体となる場合が多く、内陸埋め立ては民間設置が多いと言われており、最近では埋立地の設置に住民からの反発が増えているため、埋立地の新規設置が難しくなっています。
この問題は今後もより産業廃棄物処理業者・産業廃棄物排出事業者の負担を増やしていくでしょう。
h2:マニフェスト制度について
マニフェスト制度とは、排出事業者が排出する産業廃棄物の種類・数量・処分を委託する産業廃棄物処理業者名などを記載し、産業廃棄物の流れを確認するための書類です。
産業廃棄物の処理責任は排出事業者にあると説明しましたが、産業廃棄物処理業者に産業廃棄物の処理・処分を委託しても、その責任が全て業者に委ねられるのではありません。
万が一、産業廃棄物処理業者が不法投棄を行った場合には、委託元である排出事業者も罰せられることになるのです。
現在は最終処分場が不足しているため、処理費用が増加しており、悪質な産業廃棄物処理業者の中には委託された産業廃棄物を不法投棄するような業者も存在します。
不法投棄された産業廃棄物は地下水などを通して環境を汚染し、周囲に暮らす人の健康被害につながってしまう恐れもあるでしょう。
排出事業者と産業廃棄物処理業者でマニフェストを交わすことで、排出事業者は契約内容通りに産業廃棄物が処理されたのかを確認できるようになります。
マニフェストを交わすタイミング
マニフェストは排出事業者が産業廃棄物の処分を産業廃棄物処理業者と委託する際に作成します。
マニフェストを交わすタイミングは産業廃棄物を処分する過程で複数回あり、その度に契約通りに工程が進んでいるのかが確認できるシステムです。
マニフェストを交わすタイミングの例は下記の通りです。
- 排出事業者から集荷運搬業者に産業廃棄物が収集・運搬される時
- 産業廃棄物が収集・運搬されて中間処理業者に引き渡される時
- 中間処理が済んだ産業廃棄物が再度収集運搬業者によって運搬される時
- 収集運搬業者が最終処分業者に産業廃棄物を引き渡す時
このようにマニフェストは産業廃棄物が処理・処分される流れに沿って交付・返送が繰り返され、産業廃棄物とともに移動します。
また、マニフェストは排出事業者と、受け取った産業廃棄物処理業者の両方で5年間保管することが義務付けられているのです。
マニフェストの交わし方
マニフェストには紙マニフェストと電子マニフェストの2種類があり、それぞれにメリット・デメリットが存在するものの、運用方法は同じです。
紙のマニフェストはすぐに作成でき、産業廃棄物の処理・処分を委託する機会が少なければ労力を最小限に抑えられるものの、紛失リスク・記載間違えや記載漏れが起こりやすいというデメリットがあります。
電子マニフェストはリアルタイム閲覧が可能で、特に産業廃棄物の排出量が多い排出事業者では事務処理の効率化が期待できます。しかし、ある程度の導入費用が必要で、産業廃棄物処分に関わる全ての関係者がシステムを利用しなくてはいけないというデメリットも存在します。
また、これまでは自由に紙のマニフェスト・電子マニフェストが選択可能でしたが、2020年4月に施行された産業廃棄物処理法の改正によって「2年前に年間50t以上特別管理産業廃棄物を輩出していた事業所について、その事業所の特別管理産業廃棄物は電子マニフェストを利用すること」と定められました。
産業廃棄物処理業者によっては、紙マニフェストの発行や電子マニフェスト対応によって排出事業者の事務的負担を軽減しています。
関連ページ
お問い合わせ
CONTACT